ポータブルスキルとは
エンジニア問わずキャリアを築くうえで、技術力(テクニカルスキル)だけでなく「どんな職場・業界でも通用するスキ(ポータブルスキル)」を身につけることが重要だと考えています。
SESエンジニア焦点に考えると「プロジェクトごとに現場が変わる」特性があるため、このスキルがあるかどうかで 市場価値や単価に大きな差が生まれます。
では、具体的にポータブルスキルとは何か? どのように鍛えればいいのか?を私の考えを解説していきます。
ポータブルスキル = どんな職種・業界でも活かせる「持ち運び可能なスキル」
ポータブルスキルとは、業界や職種を問わず活かせるスキルのことです。
テクニカルスキル(プログラミング、サーバ構築など)は特定の業務に依存しますが、ポータブルスキルはどんな環境でも役立つスキルです。
下記は厚生労働省が定義しているポータブルスキルの要素です。
引用:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23112.html)
仕事のし方 現状の把握 取り組むべき課題やテーマを設定するために行う情報収集やその分析のし方 課題の設定 事業、商品、組織、仕事の進め方などの取り組むべき課題の設定のし方 計画の立案 担当業務や課題を遂行するための具体的な計画の立て方 課題の遂行 スケジュール管理や各種調整、業務を進めるうえでの障害の排除や高いプレッシャーの乗り越え方 状況への対応 予期せぬ状況への対応や責任の取り方 人との関わり方 社内対応 経営層・上司・関係部署に対する納得感の高いコミュニケーションや支持の獲得のし方 社外対応 顧客・社外パートナー等に対する納得感の高いコミュニケーションや利害調整・合意形成のし方 上司対応 上司への報告や課題に対する改善に関する意見の述べ方 部下マネジメント メンバーの動機付けや育成、持ち味を活かした業務の割り当てのし方
ポータブルスキルを身につけることで、どの現場に行ってもすぐに活躍でき、「どこでも通用するエンジニア」になれます。
SESでは必須級なスキル
SESエンジニアは、プロジェクトごとに現場やクライアントが変わるのが特徴です。
そのため、「毎回ゼロから適応し直す」ではなく「どこへ行っても通用するスキル」を持つ方が、現場活躍しやすいです。
例えば、「新しい現場に入場する」以下の2人のエンジニアがいたとします。
| 人物像 | 特徴 | 現場での評価 | 結果 |
|---|---|---|---|
| テクニカルスキル:○ ポータブルスキル:△ | 指示された難しい作業はできるが、自分で仕事を見つけられない | 「指示したことはやってもらえるから今の仕事を引き続きやってもらおう」 | 仕事内容が変わらないので単価の上り幅が少ない |
| テクニカルスキル:△ ポータブルスキル:○ | 難しい仕事はできないが、依頼の意図をくみ取り仕事ができる | 「作業の目的を理解してくれるので任せても大丈夫」 | スキルアップのチャンスが来るので単価が上がりやすい |
評価を決めるのは相手です。また、相手の評価が上がるのは「相手の期待値を超えた場合」です。
そのため、ポータブルスキルがあると、相手の期待値を超える仕事の進め方をする可能性が高まります。
ポータブルスキルのメリット
ポータブルスキルを鍛える最大のメリットは、「自分の裁量範囲」が増えること です。
<<裁量が少ない場合>>
- 決まった作業を決まった通りに思考停止して実施する
- タスクの指示待ちになる
- プロジェクト全体を俯瞰した情報が少ない
裁量がない場合には参画しているプロジェクトへ「自分の意見や見解を採用される機会が少ない」です。
<<裁量が多い場合>>
- 与えられたタスクの進め方を決められる
- チーム内で不足している個所を見つけられる
- プロジェクト全体の動向や俯瞰した情報が多い
裁量が多い場合には参画しているプロジェクトへ「自分の意見や見解を採用される機会が多い」です。
現場の活躍度合いは参画しているプロジェクトに対して「自分の意見や見解をどの程度採用された」かで計れると考えています。
経験上、高スキルエンジニア(≒高単価エンジニア)の方の意見や見解は採用されることが多いと感じます。
単価の方程式(内的要素)
エンジニアの内部要因としての単価は、次のような要素で決まると考えています。
単価 = (テクニカルスキル × ポータブルスキル) ÷ 代替性
先日、読んだQiita記事を引用します。
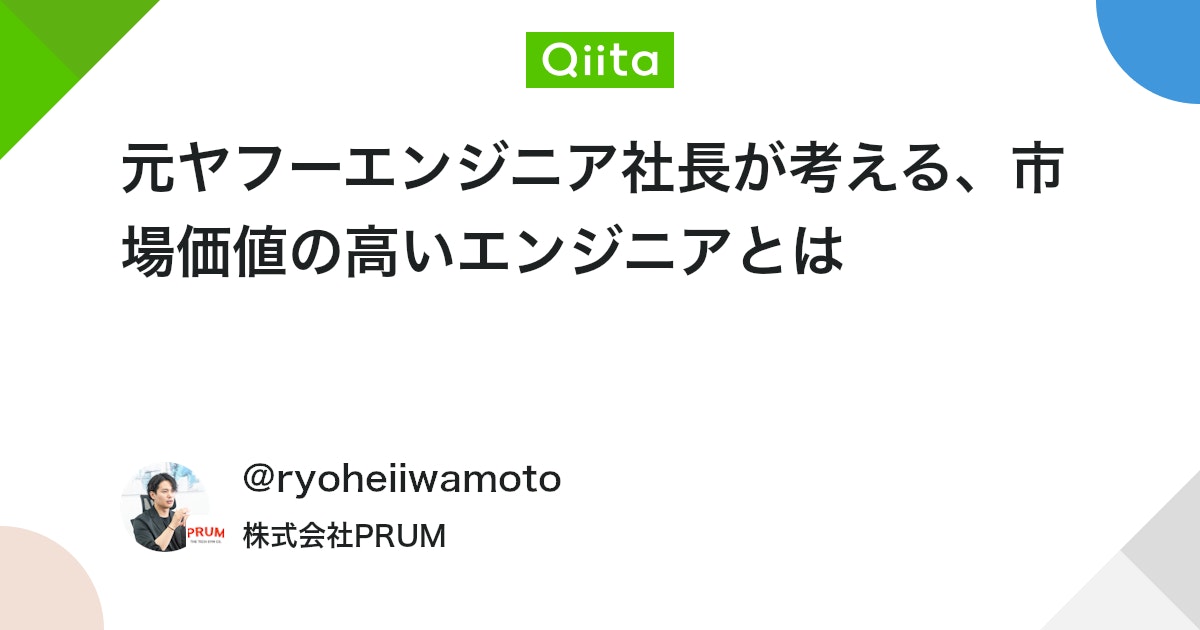
重宝されるエンジニアとは、自分の担当範囲を超えて全体に目を向けられる人。
問題を察知し、解決に向けて動ける主体性のある人です。例えば、
- スキルレベル10 × 主体性レベル3 のエンジニア
- スキルレベル5 × 主体性レベル10 のエンジニア
この場合、後者の方がチーム全体の成功に貢献できることが多いのです。
引用:元ヤフーエンジニア社長が考える、市場価値の高いエンジニアとは
エンジニアに必要なのは、プロジェクト全体を成功させる意識を持つこと。
これが主体性の重要性です。
引用元の記事では「テクニカルスキル = スキルレベル」、「ポータブルスキル = 主体性レベル」と表現されていますが、根本的な考え方は一緒です。
テクニカルスキルとポータブルスキルのどちらかを伸ばせば良いということは無く両方のスキルレベルを上げていく必要があります。
また、誰がやっても一定の品質でこなせる作業は代替されやすいので、単価は上がりにくくなります。
極端な例でいうと、コンビニのレジ担当のような仕事は、短期間の研修で誰でもできるようになるため、代わりがききやすく、単価も上がりにくい です。
ポータブルスキルの鍛え方
SESエンジニアとして、私がオススメする「ポータブルスキル」と鍛える方法を紹介します。
今回は「20代のSESエンジニア」を対象としています。
文章力
プロジェクト内の若手エンジニアのメールやチャットを見ていると言っていることが良くわからなかったり、日本語の文章として不自然になっていることを多く見かけます。
(私自身も若手の頃は上手く文章を書けず四苦八苦していました。)
業務をする上で、思っていること考えていることを相手と認識齟齬なくコミュニケーションすることを求められるため、必須のスキルです。
- メールやチャットを読んでいて「わかりやすい!」と感じた文章や言葉を少しずつ使ってみる
- 「わかりやすい!」と感じた文章を複数ピックアップして共通点を見つける
(1文が長くない、次に知りたいことが後続に書かれている、など) - 「伝えたい目的を決める → 文章の構成(見出し)を決める → 本文を肉付けする」の目的から逆算して内容を考える
問題解決能力
エンジニアはIT技術(テクニカルスキル)を駆使して、問題解決を行う職業です。
そのため、問題に対し、どのようにIT技術(テクニカルスキル)という手段を駆使して問題解決を行うのかを考える必要があります。
言うなれば、問題解決能力はIT技術(テクニカルスキル)を上手く使うスキルと言えます。
どれだけ高度なIT技術(テクニカルスキル)を持っていても、使い方が伴っていなければ意味がありません。
- 問題に対して「なぜなぜ分析」を行い根本的な原因を突き詰める
- 今の業務で無駄なプロセスが無いか、改善できる余地が無いかを考える
- 「現状(AsIs)」と「あるべき姿(ToBe)」の差を埋める行動を取り入れる
課題特定能力 / 課題選定能力
依頼されたタスクには「成し遂げたい未来(あるべき姿)がある」からこそ、細分化されたタスクを与えられます。
与えられたタスクを言われた通り行うと、成果物(アウトプット)が依頼者のイメージと合っていないことが良く起こります。
その場合、手戻りが発生するために無駄な時間になってしまいます。
そのためにも、タスクに着手する前に下記の内容を確認しておく必要があります。
- 依頼者と依頼の「背景、目的、成果物(アウトプット)」の認識を合わる
- 依頼の「背景、目的」から依頼内容とは別の成果物(アウトプット)で解決した方が効果が大きいものが無いか検討する
(効果が大きい成果物(アウトプット)があれば提案する) - 依頼の「背景、目的」が表面的な課題か、「なぜなぜ分析」をする
さらに詳しく知りたい人は下記のYoutube動画をご覧ください。
まとめ
- ポータブルスキルとは:どの職場や業界でも通用する「持ち運び可能なスキル」で、特にプロジェクトごとに現場が変わるSESにおいては不可欠です。
- メリット:ポータブルスキルがあれば、自分の裁量範囲が広がり、指示待ちから脱却して主体的に業務を推進できるため、現場での評価が高まり、高単価案件に参画しやすくなります。
- 単価の方程式:エンジニアの単価は「テクニカルスキル × ポータブルスキル」÷「代替性」によって決まります。つまり、技術力だけでなく、どこでも通用する柔軟なスキルがあると単価向上に直結します。
- 鍛え方:文章力、問題解決能力、課題特定・選定能力などを意識し、現場での経験や自主学習、改善提案を積極的に行うことで、ポータブルスキルは磨かれます。




